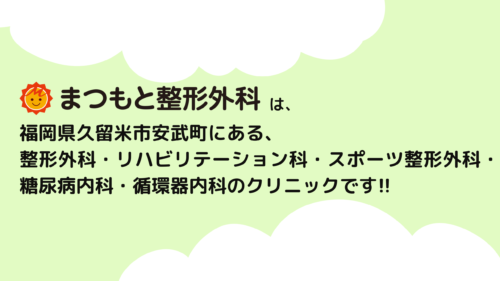
糖尿病内科・循環器内科のクリニックです
第2弾は心不全の原因から治療までお話します。
心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、心臓が全身に血液を適切に送り出せなくなった状態です。心不全の改善と進行予防には、生活習慣の見直しや早期治療が大切です。
まず、心不全の発症メカニズムや一般的な原因を理解しましょう。高齢者における心不全の特徴にも触れ、次に心不全の診断と検査法について紹介します。心不全の症状や診断への流れ、心不全を評価する基本的な検査について説明します。
心不全治療の最新情報についても詳しくご説明します。
心不全の概要と原因
心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、心臓が適切に血液を全身に送れなくなる状態です。心不全は様々な原因と疾患により引き起こされます。息切れ、呼吸が苦しい、胸が苦しい、足のむくみ(浮腫)などの症状を示すことが多いです。
心不全の原因は多岐に渡りますが、高血圧による心肥大、冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)、心臓弁膜症、心筋症、不整脈、甲状腺疾患(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)などが挙げられます。
心不全の予防としては、生活習慣の改善や早期治療が大切です。適度な運動や健康的な食生活、禁煙、禁酒、肥満の改善やストレス解消は心臓に良い影響を与えます。
心不全の発症メカニズムを解説
心不全の発症メカニズムは、心臓のポンプ機能低下と体内の循環障害に基づきます。心臓のポンプ機能の低下が進行すると、血全身に血液は送れなくなり、全身の臓器に必要な酸素や栄養が十分届かなくなります。
また、心臓の収縮機能や拡張機能が低下することで、血液が逆流し、肺や体内で水分が貯留されます(浮腫)。
高齢者における心不全の特徴
高齢者の心不全は、高血圧や不整脈、心臓弁膜症などで慢性的に心臓に負担がかかって徐々に心臓のポンプ機能が衰えることが多いです。しかし、急性心筋梗塞などでは急激に心機能が低下して心不全に陥ることがありまうす。高齢者においては、定期的な診療や生活習慣の改善が重要となります。
心不全の診断と検査
心不全の診断は、問診、聴診、胸部レントゲン、心電図、心エコー、血液検査(BNP)などから医師が総合的に判断して診断します。主な症状には、息切れ、むくみ(浮腫)、疲労感、呼吸苦、夜間の咳などがあります。これらの症状は、心臓の機能が低下し、血液の循環が悪くなることで起こります。
まず、症状や既往歴を聞き取り、心不全の可能性を疑うことが大切です。その後、上述したように様々な検査を行い、心臓の機能や状態を詳しく調べます。これにより、心不全の原因や進行度を特定し、適切な治療が選択されます。
早期に診断が確定されることで、病気の進行を遅らせ、予後の改善が期待できます。

定期的な健診が重要
心不全治療の治療
心不全は、心臓が体内に十分な血液を送り出す能力が低下する状態ですので、この状態を改善させるためには適切な治療が必要です。
心不全治療は、病気の原因や症状、進行度によって異なります。一般的な治療法としては生活習慣の改善、薬物療法、運動療法などが挙げられます。
従来の利尿剤やACE阻害薬のほか、新たな薬剤も注目されています。
また、心臓ペースメーカーや心房細動の遮断を行うカテーテルアブレーション手術も進化しています。
重症の場合、心臓移植や人工心臓といった治療法が選択されることもあります。
心不全治療法については、医師と相談し、自分に最適な治療法を選択することが重要です。
薬物療法で心不全を改善する
心不全改善のために、薬物療法が重要な役割を果たします。
– ACE阻害薬やARB:血管の収縮を抑えて、心臓の負担を減らします。心筋リモデリングの抑制効果もあります。
– β-遮断薬:心臓に負担を与える自律神経やホルモンの作用を抑制し、心臓の動きを落ち着かせます。心拍数の減少と心筋消費酸素量の低下が期待できます。
– 利尿剤:体内の過剰な水分や塩分を排泄し、息切れや浮腫(むくみ)を改善します。
-SGLT2阻害薬:元々は糖尿病薬です。血液中の余分な糖を尿として排泄するため、血糖値の改善だけではなく体重減少や血圧低下の効果もあります。
-ARNI:アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)とネプリライシン阻害薬を組み合わせた合剤です。血圧を下げる効果だけでなく、体内の余分な水分を排泄して心臓への負担を軽減させます。
-ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬:アルドステロンの働きを阻害する薬剤です。血圧を下げる作用を持ちます。心臓の肥大、腎機能の低下などに関わるアルドステロンの働きを抑えるため、慢性心不全、糖尿病性腎症の治療に使われることもあります。

適切な内服薬の選択が重要
ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)
心不全の原因となっている不整脈に対してペースメーカーを設置することがあります。また、心不全は死につながる致死性不整脈が生じることもあります。抗不整脈薬で効果が認められない場合は心臓突然死を予防するために植込み型除細動器(ICD)の装着が検討されることもあります。
水分バランスを整える利尿剤の使用
心不全では体内に過剰な水分が貯まるために、水分バランスの調整が重要になります。利尿剤は、この目的のために使用されます。利尿剤は、腎臓での水分とナトリウムの再吸収を抑えることにより、尿量を増やし、体内の水分バランスを調整します。結果として、水分の貯留による呼吸困難や浮腫が軽減されます。
しかし、過剰な利尿剤の使用は、脱水症状や腎機能の低下につながることがあるため、医師の指示に従って投与量や使用頻度を調整することが必要です。
生活習慣の改善で心不全を予防
心不全は、心臓のポンプ機能が低下して心臓が全身に十分な血液を送り出せない状態です。心不全の原因は多岐にわたりますが、高血圧や糖尿病、肥満、狭心症、心筋梗塞、不整脈、ストレスといった病気が影響しています。これらの病気が進行することで、心臓に負担がかかり、心不全のリスクが高まります。しかし、生活習慣の改善を行うことで、心不全の予防が可能です。具体的には、適度な運動や食生活の見直し、血圧や血糖値の管理が効果的です。また、定期的に循環器専門医や糖尿病専門医で診察を受け、早期発見・早期治療を行うことが重要です。
予防に役立つ運動や食事のポイント
まず運動についてですが、適度な運動が心不全予防には欠かせません。心臓の機能を保つため、ウォーキングや自転車などの有酸素運動がおすすめです。無理のない範囲で継続して行いましょう。食事に関しては、塩分や糖分の摂取を注意し、野菜や果物、魚などのバランスの良い食事が大切です。また、喫煙やアルコール摂取を控えることで、心臓への負担を軽減できます。心不全予防のためには、これらの生活習慣を見直し、健康的な生活を送ることが重要です。
定期的に血圧や血糖値を管理する必要性
高血圧や糖尿病は、心不全の大きなリスク要因となります。高血圧が続くと心臓には大きな負担がかかるため、心肥大が起きて心不全に至ります。糖尿病では、心臓の冠動脈に動脈硬化が進むことで狭心症や心筋梗塞が引き起こされます。重症化すると心臓のポンプ機能が低下し心不全を発症します。そのため、定期的に血圧や血糖値を測定し、管理することが非常に大切です。家庭用の血圧計や血糖測定器を用いて自己管理ができ、定期的に循環器専門医や糖尿病専門医の診察を受けましょう。
心不全のまとめ
心不全は、適切な治療や管理を行うことで、症状の改善、進行予防、生活の質を高めることができます。早期発見・早期治療が重要なため、異常を感じたら速やかに医師の診察を受けましょう。まずは生活習慣の改善から始めて、心不全の予防に努めることが大切です。
【参考文献】
・日本心臓財団,心不全の初期サイン https://www.jhf.or.jp/check/heart_failure/09/
・日本心臓財団,心不全とは https://www.jhf.or.jp/check/heart_failure/02/
