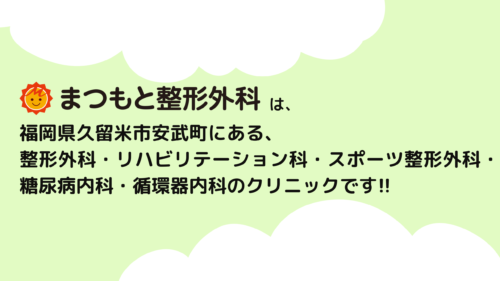
糖尿病内科・循環器内科のクリニックです
今週より新シリーズが開始します!今回のテーマは『心不全』です。
第1弾は心不全の症状や原因についてお話します。
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、心臓が血液を体内に適切に送り出せなくなり循環不全が生じる病気です。生活の質を低下させるだけでなく、重症化すると命に関わる重大な病気です。
心不全の原因には、高血圧による心肥大、冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)、心臓弁膜症、心筋症、不整脈、甲状腺疾患(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)などが挙げられます。これらのリスクを把握し、早期発見が大切です。
また、心不全の症状は初期段階から進行期まで様々です。急性心不全と慢性心不全に分けられますが、息切れ(息がしずらい)や呼吸苦(呼吸が苦しい)、倦怠感、食欲不振、足のむくみ、体重増加、夜間の咳などが現れることもあります。
心不全の診断には、問診、聴診、胸部レントゲン写真、心電図や心エコー、血液検査(BNP)などで総合的に判断します。
心不全の早期発見と適切な管理が鍵となるため、本記事を参考にして、自身の健康を見直してみましょう。
心不全に至る原因と危険因子
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、体内血液の循環が低下します。原因と危険因子を知ることは予防と早期対処につながります。主な原因は、高血圧、冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)、心臓弁膜症などが挙げられます。危険因子としては、高齢者(65才以上)、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症)、肥満、家族歴、喫煙、運動不足、ストレス、飲酒などが影響します。
また、既往症や他の疾患がある場合も、心不全のリスクが高まります。重要なのは、これらの危険因子を把握し、生活習慣を改善することです。定期的な健康診断で血圧などをチェックし、健康状態とその他の病気との関連を評価することが必要です。
高血圧や糖尿病が引き金となる場合
高血圧や糖尿病は、心不全の引き金となることがあります。高血圧が続くと心臓には大きな負担がかかるため、これに対応しようと心筋が分厚くなり、心肥大が起きて心不全が引き起こされます。糖尿病では、心臓の冠動脈に動脈硬化が起こります。その結果として、狭心症や心筋梗塞を引き起こし、重症化すると心臓のポンプ機能が低下し心不全を発症することがあります。
このため、高血圧や糖尿病の方は、定期的な受診や薬物療法を行い、血圧や血糖値のコントロールが重要になります。また、生活習慣の見直し、適切な体重管理、適度な運動、禁煙、節制などが予防策となります。
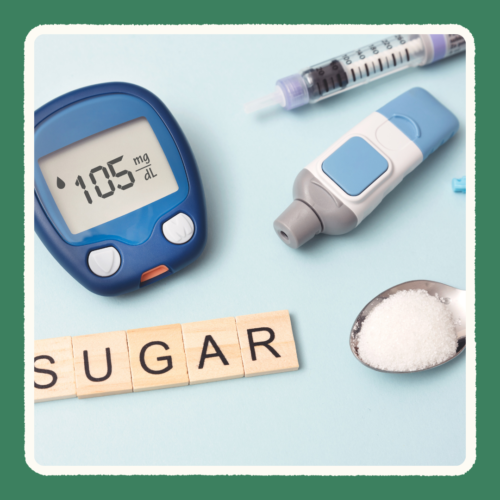
糖尿病もリスクとなる
冠動脈疾患や心筋梗塞から進行するケース
冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)は、心不全を引き起こす原因となります。心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈に動脈硬化が起こると、冠動脈の血流が制限され、心筋への酸素供給が不足することで、心臓のポンプ機能が低下します。重症化し、心筋梗塞を起こすと心臓の筋肉がダメージを起こすために、心不全へ進行することがあります。
これらの症状を予防・管理するためには、生活習慣の見直し、適切な診療、薬物療法などが有効です。また、重症化すると命の危険もあるために、症状が現れたら速やかに医療機関を受診することが重要です。
心不全の症状:初期段階から進行期まで
心不全の症状は初期段階から進行期までさまざまです。初期段階では、息切れ、倦怠感、足のむくみなどが現れます。これらは日常生活に支障をきたすことが多く、この初期段階の症状に早く気付くことが大切です。
進行すると、うっ血性心不全に陥り、呼吸困難、夜間の咳、胸の圧迫感、寝る際の呼吸苦(仰向けで寝れない)などの症状が表れます。さらに重症化すると、全身の循環が悪化し、肝臓や腎臓などへの影響が現れることもあります。
早期発見と適切な治療が重要ですので、症状が出たら速やかに医療機関を受診しましょう。

心不全の症状の一つ
急性心不全と慢性心不全
急性心不全は、突然発生する心機能不全によって生じる症状で、原因としては、冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)や心筋炎などが挙げられます。症状としては急激な呼吸困難、息切れ、胸痛が特徴的です。
一方、慢性心不全は、心臓のポンプ機能の低下が徐々に進行するために、疲労感、息切れ、むくみの症状が次第に悪化していきます。
生活習慣の改善や治療によって、心不全は治療可能であり、また進行を遅らせることもできます。
息切れや足のむくみはうっ血性心不全の症状
うっ血性心不全の症状は、心臓のポンプ機能が低下し、血液の循環が滞り、水分が体内に溜まることで起こります。肺の水が貯まると呼吸苦や咳の症状が、足に水が貯まると足のむくみが現れます。
重症化すると、呼吸が苦しくなり、酸素の吸入が必要になります。
食欲不振や体重増加の兆候
心不全の進行に伴い、食欲不振や体重増加が見られることがあります。体内の血液循環が悪化し、内臓への血液の供給が減少することで、食欲不振が生じることがあります。体重増加は、体内の水分が正常に排出されず、むくみとして体内に水が蓄積していくため起こります。これらの症状が現れた場合は、病状の進行を疑い、速やかに受診が必要です。
心不全診断のための検査方法
心不全の診断には、問診、持病(既往歴)、聴診、胸部レントゲン検査、心電図や心エコー検査、血液検査(BNP)などから判断します。
心電図や心エコー検査での評価
心不全の診断には、心電図やエコー検査が用いることがあります。心電図は、心臓の電気的活動を記録する検査で、心不全の原因となる、狭心症、心筋梗塞、不整脈の有無を確認できます。一方、心エコー検査では、心臓の収縮力や弁膜症の有無な心臓の動きや機能を詳しく調べます。
これらの検査は、心不全の原因や心不全の程度を把握するのに役立ち、治療方針を立てる上で重要な役割を果たします。また、定期的に検査を受けることで、病状の進行や治療効果を評価し、早期に問題が発見した場合には、適切な対処が可能となります。
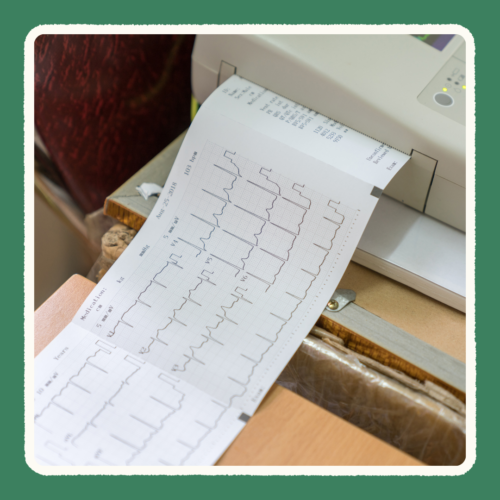
心不全の原因や程度を調べる心電図検査
血液検査でのBNPやNT-proBNP値の確認
血液検査において、心不全の診断に役立つ指標としてBNPがあります。心臓に負担がかかることにより分泌されるBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)を測り、心不全の重症度を調べます。
BNPの値を定期的にチェックすることで、心不全の症状の進行や治療効果の評価が可能となります。
まとめ:心不全の早期発見と適切な管理が鍵
心不全の早期発見と適切な管理は、病状の進行を遅らせ、生活の質を向上させるために大切です。心電図やエコー検査、血液検査(BNP)は症状が悪化する前に、定期的にかかりつけ医で検査及び管理することで、早期発見と適切な管理が可能となります。
【参考文献】
・日本心臓財団,心不全の初期サイン https://www.jhf.or.jp/check/heart_failure/09/
・日本心臓財団,心不全とは https://www.jhf.or.jp/check/heart_failure/02/
