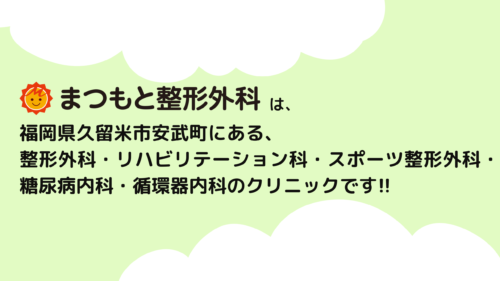
糖尿病内科・循環器内科のクリニックです
睡眠時無呼吸症候群(SAS)に悩まされている方や、その予防策や治療方法を知りたい方必見!睡眠時無呼吸症候群の概要、症状、検査方法、治療法を徹底解説。自宅での簡易検査から専門的な検査・治療まで、睡眠時無呼吸症候群改善のための情報をお伝えします!
この記事では、睡眠時無呼吸症候群の概要から影響、検査方法、治療方法まで徹底解説いたします。
– 睡眠時無呼吸症候群とは?
– 主な症状と日常生活への影響
– 合併症のリスクと予防方法
– 自宅でできる簡易検査
– スクリーニング検査の詳細
– 精密検査:ポリソムノグラフィ(PSG)
– 検査結果の読み方と診断基準
– CPAP療法の効果と取り組み方
– いびき改善手術とその適応条件
– 生活習慣改善で無呼吸を予防
– 睡眠時無呼吸症候群専門の病院・外来
睡眠時無呼吸症候群に関する情報を網羅し、症状の改善や、治療・予防に役立つことを目指しています。この記事を通じて、睡眠時無呼吸症候群に関する理解が深め、より適切な治療法や予防策を学んでいきましょう!
睡眠時無呼吸症候群の概要と影響
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が繰り返し止まる病気で、その原因となる要因は様々です。肥満や高血圧、糖尿病等の健康問題や生活習慣病が関係している場合が多く、自覚症状がないこともあり、症状が進行しやすい特徴があります。睡眠時無呼吸症候群の検査と診断は病院や専門医療機関で行われますが、簡易検査は自宅でも可能です。治療方法としてCPAP療法や手術等の選択肢があり、適切な治療を受けることで日常生活の質が改善されます。また、睡眠時無呼吸症候群は、交通事故等のリスク要因となることもあるため、早期に受診・治療が重要です。さらに、予防策や健康習慣の見直しも大切です。

日中眠気に襲われることも
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が一定時間以上途切れる病気です。中枢性睡眠時無呼吸(CSA)と閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)があり、約9割の方が閉鎖性睡眠時無呼吸に該当します。閉塞性無呼吸の主な原因は、肥満や扁桃腺の肥大、あごの形態(下あごが小さい、などの素因があり、舌や軟口蓋の筋肉が緩むことによる気道の閉塞が起きます。これにより、酸素が不足し、重症の場合は脳波や心臓の動きに変化が生じます。結果として、眠りが浅くなり、睡眠の質が低下していきます。状態が悪化すると、日常生活や健康に大きな影響を与えることがあります。
主な症状と日常生活への影響
睡眠時無呼吸症候群の主な症状はいびき、疲労感、頭痛、昼間の眠気等です。これらの症状は日常生活に悪影響を与えることがあり、仕事や家庭、運転等の注意力が低下し、事故リスクが高まる恐れがあります。また、睡眠の質が低下することで、健康状態にも影響が出ることがあります。また、放置すると血糖値や血圧が上昇し、高血圧や糖尿病、脂質異常症などさまざまな生活習慣病が引き起こされることがわかっています。結果として、動脈硬化が進んだり、心臓や脳血管の負担が増し、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。早期の受診と治療が重要であるため、症状がある場合は専門医に相談してください。
合併症のリスクと予防方法
睡眠時無呼吸症候群は、多くの合併症のリスクが伴います。これには、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中等が含まれます。予防方法としては、体重管理、適度な運動、バランスの良い食生活、禁煙・減酒等の健康習慣の見直しが挙げられます。また、就寝前のリラックスタイムの確保や、寝る姿勢の工夫も効果的です。さらに、定期的な検診や症状のモニタリングが大切です。症状がある場合は、専門医に相談し、適切な治療を行ってください。
睡眠時無呼吸症候群の検査方法
睡眠時無呼吸症候群の診断は、問診や診察を行い、自宅での簡易検査で診断を付けることができます。具体的には、簡易検査、スクリーニング検査、精密検査(ポリソムノグラフィ)といった手法があります。
まずは自宅でできる簡易検査
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合、まずは自宅で簡易検査を行うことができます。簡易検査は、患者自身が自宅で無呼吸やいびきの状態を記録し、医師に報告する方法です。具体的には、日常生活での症状観察や、鼻・口呼吸のチェック、呼吸停止回数を数える方法があります。症状が重症化している状態や他の疾患との関連性を調査するため、医療機関での精密検査が推奨されることがあります。
スクリーニング検査(簡易型PSG)の詳細
スクリーニング検査(簡易型PSG)は、睡眠時無呼吸症候群の可能性を見極めるための検査です。就寝時に携帯型の装置を装着して、睡眠中の酸素飽和度、呼吸数、呼吸状態などを調べます。この検査は、入院する必要はなく、自宅で行うことができます。
簡易型PSGは自宅で検査できることが最大のメリットで、原則として保険適応です。
精密検査:ポリソムノグラフィ(PSG)
ポリソムノグラフィ(PSG)は、睡眠時無呼吸症候群の診断のための最も正確な検査方法です。一晩中の睡眠を監視し、脳波や酸素飽和度、心電図、筋電図、眼球運動などの生体情報を測定します。これにより、無呼吸の発生回数や持続時間、低酸素状態による影響などを詳細に把握することができます。PSGは主に病院や専門の睡眠検査センターで実施されます。検査結果に基づいて、治療法が決定されることが一般的です。
検査結果の読み方と診断基準
検査結果の読み方には、AHI (Apnea Hypopnea Index) という指標が重要であり、これは1時間あたりのいびきや呼吸停止の回数を示す。AHIが低いほど、症状が軽いと言える。診断基準は以下の通りです。
– AHI 5未満: 正常
– AHI 5以上15未満: 軽度の睡眠時無呼吸症候群
– AHI 15以上30未満: 中度の睡眠時無呼吸症候群
– AHI 30以上: 重度の睡眠時無呼吸症候群
診断には、病院での精密検査 (PSG) や自宅での簡易検査 (SAS) が用いられる。専門医の診断と協力を得て、適切な治療方法を選びましょう。
治療方法と改善への道
治療方法は、症状の軽重や原因により異なる。軽度の場合は、生活習慣の改善や体重の減少が効果的である。
中度~重度の場合は、以下の治療方法が選択されることが多くなります。
– CPAP療法: 機器を使用し、空気の圧力で気道を開放する
– 睡眠時口腔内装置: 下顎を前方に引くことで気道を確保する
– 手術療法: 気道の障害部位に対する手術
治療方法の選択や改善への道には、医師との綿密な相談が必要である。また、治療に取り組むことで合併症のリスクを減らすことが重要です。

CPAP治療の様子
CPAP療法の効果と取り組み方
CPAP療法は、睡眠時無呼吸症候群の治療に最も効果的な方法とされています。機器は、顔に装着するマスクから空気を送り込み、気道を開放することで、いびきや呼吸停止を予防します。
CPAP療法を適切に行うことで、効果が期待されます。
– 睡眠の質の改善
– 日中の眠気の軽減
– 合併症のリスク低減 (高血圧、糖尿病、脳卒中など)
取り組み方としては、まず医師に相談し、適切な機器の選択や使い方を学ぶことが大切です。また、継続的に使用することで効果が最大化されるため、毎晩の睡眠時に装着することが重要である。CPAP療法に慣れるまでに時間がかかることもあるが、効果が実感できれば生活の質が大幅に向上します。
手術とその適応条件
手術は、睡眠時無呼吸症候群の原因となるいびきの問題を解決するために行われます。
〇適応条件
– 重度のいびきや睡眠時無呼吸症候群がある
– CPAP療法などの治療法が効果がないまたは忍容できない場合
– 鼻や口腔、咽頭、気道などの構造的な異常が原因でいびきが発生している
手術方法にはいくつかの種類があり、患者様の状態や症状により適切な手術が選択されます。手術によって、いびきや無呼吸が改善され、生活の質が向上することが期待できます。
生活習慣改善で無呼吸を予防
生活習慣改善は、無呼吸の予防に大きな効果があります。以下の点に注意して生活習慣を見直すことで、無呼吸のリスクを軽減できます。
– 肥満の改善: 体重を減らすことで気道の圧迫が緩和され、無呼吸が改善されることが多いです。
– 喫煙・飲酒の制限: 喫煙・飲酒は気道の筋肉を緩めて無呼吸を悪化させる原因となります。
– 睡眠習慣の改善: 定期的な睡眠時間や適切な寝具、横向き寝などのアプローチも無呼吸の予防に役立ちます。
睡眠時無呼吸症候群の適切な診療科:耳鼻科、循環器科、呼吸器科
睡眠時無呼吸症候群は適切な診療科や専門医に診てもらうことが大切です。睡眠時無呼吸症候群を専門的に診る診療科は耳鼻科、循環器科、呼吸器科になります。ホームページなどで、睡眠時無呼吸症候群のページが作成されているのか、確認してみるのがよいと思います。
睡眠時無呼吸症候群を専門的に診ているクリニックでは精密な検査や適切な治療法が提供されるため、効果的な治療が期待できます。また、医師やスタッフは睡眠時無呼吸症候群に関する知識や経験が豊富であり、患者に対して適切なアドバイスやケアが提供されます。
検査から治療までのステップ
〇睡眠時無呼吸症候群の治療プロセス
1. 症状やリスクがある場合は専門の病院・クリニックで診察を受ける
2. 必要に応じて検査を受け、診断を受ける
3. 治療法(CPAP療法、生活習慣改善、手術など)が決定される
自分に合った治療法を見つけていきましょう🍀
当院では睡眠時無呼吸症候群の専門的な検査から治療までをご提案することができます。
いびきで悩んでいる・疲れが取れない・頭痛がひどいなどお悩みの方。ぜひ一度まつもと整形外科 内科へお問い合わせください。
生活習慣病を得意とする糖尿病専門医と循環器専門医が在籍しているために診断から継続的な生活習慣病として長期的な治療と生活指導が可能です。ぜひお問い合わせください🍀
来週は睡眠時無呼吸症候群に効果的な食事や栄養についてお話しします🍀どうぞお楽しみに!!
初診のWEB予約はこちらから!👇
ここをタップしていただくと内科初診:初診の予約画面に移行します
TEL予約はこちら
当院の睡眠時無呼吸症候群の治療についてはこちらから!!👇
📖参考文献📖
・日本医師会,睡眠時無呼吸症候群 https://www.med.or.jp/forest/check/mukokyu/02.html
・日本呼吸器学会,睡眠時無呼吸症候群 https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/i/i-05.html
