心不全とともに生きる患者さんを支える専門家
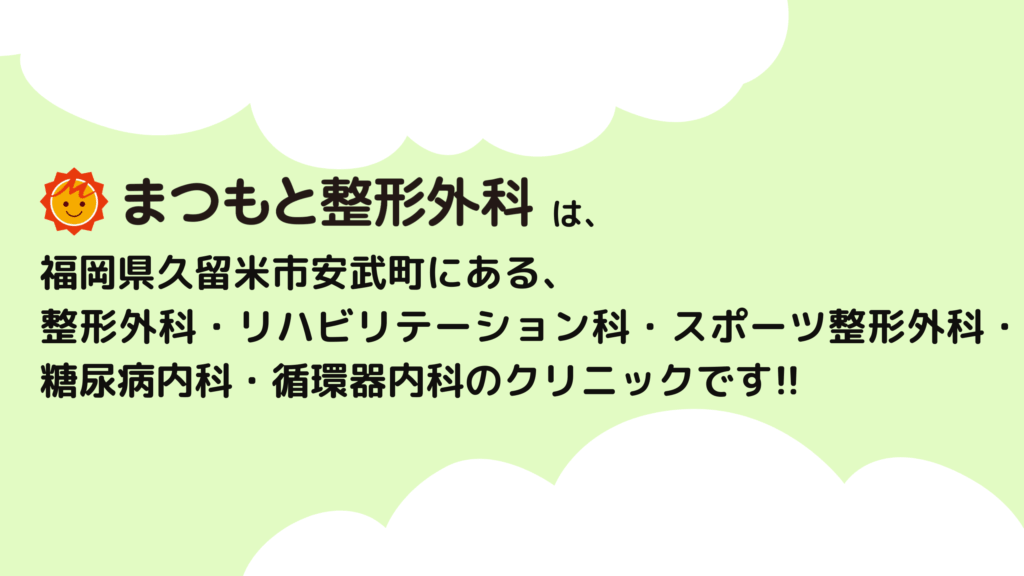
糖尿病内科・循環器内科のクリニックです
~心不全療養指導士の役割と当院での取り組み~
近年、心不全という病気が日本の高齢化とともに大きな注目を集めています。心不全は「心臓の機能が低下して、全身に必要な血液を送り出せなくなる」状態の総称です。慢性化しやすく、入退院を繰り返すケースも多いため、医療機関での継続的なサポートが必要です。
このような患者さんの生活を支え、入退院を防ぎ、よりよい日常生活が送れるように導いていく専門職が「心不全療養指導士」です。当院には、この資格を持つスタッフが在籍しており、チーム医療の一員として心不全患者さんの支援を行っています。
本日は、この心不全療養指導士について、どのような役割を担っているのか、そして当院での具体的な関わりや取り組みについてご紹介いたします。
心不全療養指導士とは?
心不全療養指導士とは、日本循環器学会および日本心不全学会が認定する資格で、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士などの医療職が対象です。心不全の病態、治療法、生活指導などについて専門的に学び、患者さんに適切な療養支援を提供する役割を担います。
心不全は、症状が一時的に落ち着いても再発しやすく、日々の生活習慣の積み重ねが予後に大きく影響します。そのため、患者さんの理解と実践が非常に重要です。心不全療養指導士は、医師の診療を補完しながら、生活指導や服薬管理、リハビリ支援などを多職種連携の中で実施していきます。
当院の心不全療養指導士の関わり
当院では、心不全療養指導士の資格を持つ看護師が在籍しており、循環器内科専門医と連携しながら、患者さんの状態や生活環境に応じた支援を行っています。
1. 生活指導
心不全患者さんにとって、塩分や水分の摂取制限、体重管理、運動のバランスは非常に重要です。指導士は、患者さん一人ひとりの生活背景や理解度に合わせて、無理のない生活習慣の改善を提案します。
たとえば、
-
食事に含まれる「隠れ塩分」の具体例
-
外食時のメニュー選びのコツ
-
日常での軽い運動の取り入れ方
といった、実践的で続けやすい内容を丁寧に説明します。
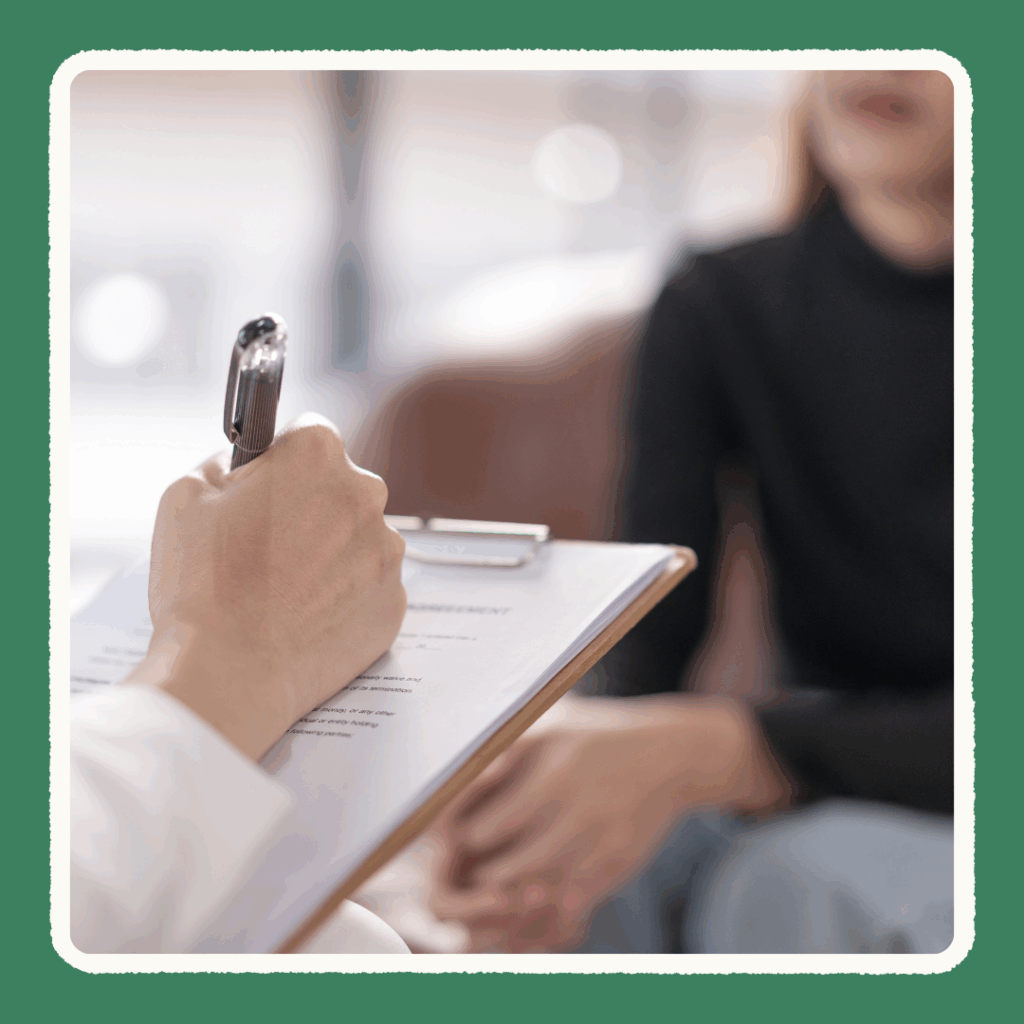
生活指導
2. 服薬指導・アドヒアランスの向上
心不全の薬物治療は、複数の薬剤が処方されることが多く、服薬の継続が重要です。しかし、高齢の患者さんにとっては、飲み忘れや副作用への不安が服薬継続の妨げになることがあります。
心不全療養指導士は、服薬の目的や注意点を丁寧に説明し、患者さんの「納得感」を高めながら、自立した服薬管理をサポートします。また、ご家族とも情報共有を行い、家庭でのサポート体制を整えることも重要な役割の一つです。
3. 体調変化のセルフモニタリング支援
心不全は体重の急な増加や呼吸困難など、微細な変化が再悪化のサインになります。指導士は、体重・血圧・脈拍・尿量などのセルフチェックの方法を指導し、異常があった際の対応方法についても事前にお話しを行うなどし患者さまの不安の除去に努めています。
また、再発の早期発見のために、受診時のチェックも行っています。
チーム医療の中での役割
心不全療養指導士は、医師や看護師、理学療法士、薬剤師といった多職種との連携の中で、橋渡し的な存在として活躍します。
当院では、医師を含めたチームカンファレンスを行い患者さんの状態に応じたケアプランを多職種で協議しています。
患者さんとご家族へのメッセージ
心不全という病気は、一度診断されると完治は難しく、継続的な治療が必要です。医療機関と正しく連携し、体調管理に気を付けて、継続的な治療を行うことで再発を防ぎ、よりよい生活を送ることが可能です。
当院の心不全療養指導士は、患者さん一人ひとりの声に耳を傾け、生活に寄り添いながら支援を行っています。お困りごとや不安があれば、いつでもご相談ください。医師だけでなく、専門のスタッフがチームでサポートいたします。
まとめ
-
心不全療養指導士は、心不全の再発予防と生活支援を担う専門職です
-
当院では、生活指導・服薬支援・セルフチェックの支援を丁寧に行っています
-
多職種連携を通じて、患者さんとご家族の安心につなげています
循環器疾患とともに生きる皆さまの、少しでも力になれるよう、当院ではこれからも研鑽を続けてまいります。お気軽にご相談ください。
当院には循環器内科専門医、心不全療養指導士・保健師が在籍しています。お気軽にご相談下さい🍀
初診のWEB予約はこちらから!!👇
ここをタップしていただくと内科初診:初診の予約画面に移行します✨
TEL予約はこちら
📞0942-27-0755📕参考文献
