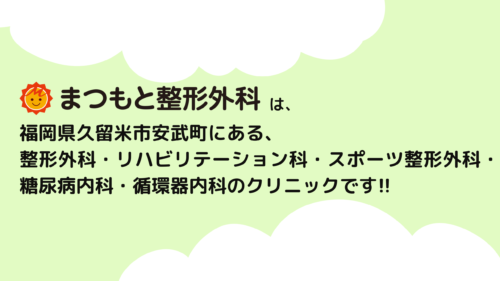
糖尿病内科・循環器内科のクリニックです
今週は脂質異常症に必要な検査から治療までお話します☺️
脂質異常症の診断と指標:検査結果の詳細に基づく適切な治療法
脂質異常症とは、血液中のLDL(悪玉)コレステロールやトリグリセライド(中性脂肪)が必要以上に増えるか、HDL(善玉)コレステロールが減った状態のことです。動脈硬化のリスクを高めるため、心筋梗塞や脳梗塞などの命に関わる重大な疾患を引き起こすことがあります。
医師による問診、検査など評価が重要になります。
検査では、血液検査でHDL(善玉)コレステロール、LDL(悪玉)コレステロール、トリグリセライド(中性脂肪)の値を調べます。診断基準は、LDLコレステロールが140 mg/dL以上、HDLコレステロールが40 mg/dL以下、またはトリグリセライド(中性脂肪)が150 mg/dL以上ですが、年齢や性別、既往症などの背景から治療方法や薬について決めていくことになります。
検査結果に基づき、薬物療法や食事療法、運動療法などが適宜組み合わせます。薬物療法は、病状や脂質値、既往症によって選択され、副作用に注意しながら使用します。
患者様と医師の密なコミュニケーションが重要であり、定期的な診察と検査が効果的な治療の鍵となります。

患者様と医師の密なコミュニケーション
脂質異常症とは何ですか?
脂質異常症とは、血液中のLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)が必要以上に増えるか、HDL(善玉)コレステロールが減った状態のことです。この状態が長期的に続くと動脈硬化が進行して、狭心症や心筋梗塞、脳卒中(脳梗塞、脳出血)などの心血管疾患のリスクが高まります。特に高齢者の方では、これらのリスクが高まりますので、定期的な検査が推奨されています。
検査の重要性は?
脂質異常症は初期の段階では自覚症状がほとんどないため、多くの人が病気に気づかずに進行してしまい、最終的に命に関わる重篤な病気を引き起こすことから「サイレントキラー」とも呼ばれます。早期発見には定期的な血液検査が非常に有効です。これにより、適切な治療や生活習慣の見直しを早期に始めることができます。
検査方法について
脂質異常症の検査として空腹時に血液中の総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、トリグリセリドの4つの値を測定します。当院では、血液検査の翌日に検査結果が出ます。
検査結果の読み方
検査結果には、各脂質成分の数値が記載されています。一般的に、総コレステロールは200mg/dL以下、LDLコレステロールは140mg/dL以下、HDLコレステロールは40mg/dL以上、トリグリセリドは150mg/dL以下が理想的です。これらの数値が基準値を超える場合は、医師と相談の上、適切な治療が必要です。
生活習慣の改善による影響
食事の見直しや適度な運動は脂質異常症の管理に非常に効果的です。特に、脂肪分の多い食品を避け、野菜や果物を多く摂ること、定期的なウォーキングや水泳などの運動を行うことが推奨されます。また、喫煙は脂質異常症のリスクを高めるため、禁煙も非常に重要です。

禁煙は非常に重要
Q&A
Q1: 脂質異常症の検査はどれくらいの頻度で受けるべきですか?
A1: 一般的には、40歳を過ぎたら年に一度の検査が推奨されます。すでに脂質異常症と診断され治療中の方は、安定している場合は3~6か月に1度くらいの頻度で血液検査を行います。ただし、個人の生活習慣、健康状態(高血圧や糖尿病の併発)や家族歴によっては、より頻繁な検査が必要な場合もありますので、主治医と相談してください。
Q2: 検査の前に食事制限は必要ですか?
A2: はい、検査の前には9~12時間の絶食が必要です。ガイドラインでは朝食前の血液検査の数値で診断することが推奨されています。水分は摂取しても大丈夫ですが、コーヒーやお茶は避けるようにしてください。
Q3: 脂質異常症は遺伝しますか?
A3: 遺伝的要因も影響していることがあります。家族に脂質異常症の人がいる場合は、若いうちから定期的な検査を受けることをお勧めします。
Q4:コレステロールは下がりすぎてもよくないのですか?
A4:コレステロールは体内に必要な成分で、胆汁やステロイドホルモンの原料となります。あまり下げ過ぎると、疲労感などが出ることがあります。
Q5: トリグリセライド(中性脂肪)が高くても治療が必要ですか?
A5: 悪玉コレステロールであるLDLコレステロールは、「悪玉」の名前があるために治療しなければいけない意識があるのですが、トリグリセライド(中性脂肪)は軽視されがちです。トリグリセライド(中性脂肪)の高値は動脈硬化を進行させ、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞のリスクを高めるために治療が必要になります。
脂質異常症は早期発見が重要です。定期的な検査を受けることで、必要な治療や生活習慣の改善を行い、健康状態を良好に保つことが可能です。
脂質異常症の治療法:薬物療法から生活改善まで幅広い選択肢
高脂血症の治療には主に、生活習慣の改善と薬物療法の二つのアプローチがあります。
脂質異常症の治療法には多くの選択肢があり、薬物療法以外にも生活習慣の改善が重要になります。
– 薬物療法: スタチンやフィブラートなど、患者の症状に応じた薬物が処方されます。
– 食事療法: 食事を制限して、脂質の摂取量を減らす必要があります。脂質、特に悪玉コレステロールを減らすことができる食事内容に改善が必要です。食物繊維やオメガ3脂肪酸を摂取することが効果的です。
– 運動療法: 運動はLDL(悪玉)コレステロールが分解されて減り、HDL(善玉)コレステロールが増えます。さらに適度な運動は血液循環を改善させます。
– 禁煙: 喫煙は血管に悪影響を及ぼし、動脈硬化を促進するため禁煙が推奨されます。
– 減量: 肥満が脂質異常症の原因となり得るため、適切な体重を維持することが大切です。
治療法は患者一人ひとりの状況に応じて選択され、継続的なケアが大切です。
1、薬物療法の種類と効果:スタチン薬やフィブラート薬の適切な使用法
薬物療法には、スタチン薬やフィブラート薬があり、それぞれ異なる効果を持ちます。スタチン薬はLDL(悪玉)コレステロールを低下させ、心血管疾患の予防に役立ちます。フィブラート薬は、トリグリセライドを減少させる効果があり、症状やリスクに応じて最適な治療法を選択することが重要になります。
スタチン薬の適切な使用法には、医師の指示に従い、空腹時に服用し、副作用に注意することが重要です。一方、フィブラート薬は食事と一緒に摂取することが望ましく、脂質改善の効果が見られるまで数週間から数か月かかることを理解する必要があります。
病状やリスク要因に応じて、他の薬物療法も選択肢に含まれます。例えば、ニコチン酸薬は、HDL(善玉)コレステロールを増加させる効果があり、脂質異常症の改善に寄与します。適切な治療法を選択するために、医師と密接に相談し、薬物療法や生活習慣の変更を検討することが重要です。
薬物療法
-
- スタチン類: LDLコレステロールを効果的に下げるために最も一般的に使用される薬です。スタチンは、コレステロール合成を抑制することで、血液中のLDLコレステロールを下げます。
- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬: 小腸におけるコレステロールの吸収を抑え、血液中のコレステロールを低下させる効果があります。
- ニコチン酸: ビタミンE製剤でトリグリセリドとLDLコレステロールを低下させ、HDLコレステロールを増加させる効果があります。
- 新しい薬剤: PCSK9阻害薬は、LDLコレステロールを効果的に大幅に低下させる新しいクラスの薬剤です。
-

脂質異常症の薬物療法
治療時の注意点
高脂血症の治療を進める際には、以下の点に注意することが重要です。
-
- 定期的なフォローアップ: 治療の効果を確認し、副作用がないかを確認するために、定期的なチェックが必要です。特に薬物療法を行っている場合は、横紋筋融解症などの合併症があるために血液検査を定期的に受けることが推奨されます。
- 副作用の管理: スタチンなどの薬物は脂質異常症の治療に効果的ですが、筋肉痛や肝機能障害などの副作用が報告されています。これらの症状が現れた場合は、速やかに医師に相談し、適切な対応を取る必要があります。
- 生活習慣の継続的な改善: 薬物療法だけに依存せず、食事や運動などの生活習慣の改善を継続することが、長期的な健康維持には不可欠です。
– 食事:低脂肪で栄養バランスのとれた食事を心がけます。脂肪の摂取量を抑え、特に飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取を控える。オメガ3脂肪酸が豊富な魚や植物性食品を積極的に摂取。繊維や魚介類も好ましいです。
– 運動:適度な運動を行い、筋肉を維持し、脂質代謝を改善するのに役立ちます。
– 健康な体重:肥満の予防と適切な体重管理が脂質異常症のリスクを減らします。
– ストレス管理:ストレスを適切にコントロールし、心身の健康を維持します。
これらの生活習慣を実践することで、脂質異常症やそれに関連する疾患のリスクを低減することが期待できます。
禁煙やアルコールの制限:心血管疾患のリスクを低下させる生活習慣
禁煙やアルコールの制限は、心血管疾患のリスクを低下させる重要な生活習慣です。喫煙は、動脈硬化や高血圧の原因となり、心臓や脳の血管に悪影響を及ぼします。禁煙は、これらのリスクを大幅に減らし、健康寿命を延ばすことができます。
アルコールについても、摂取量を適切に制限することが重要です。適量のアルコール摂取は、HDLコレステロールを上昇させる効果があり、心血管疾患の予防に役立つが、摂取量が増えると、逆にリスクが高まるため注意が必要です。適切なアルコール制限によって、心血管疾患のリスクを抑えることが可能です。
定期的な健康診断と医師との相談:症状の早期発見と適切な治療の重要性
定期的な健康診断と医師との相談は、症状の早期発見と適切な治療に繋がります。健康診断では、脂質異常症の状況やその他のリスク要因をチェックできます。早期発見によって、適切な治療や生活習慣の改善が行われ、病気の進行が抑えられます。
医師との相談を通じて、治療法や予防策についての情報を得ることができます。また、自身の状況やリスクに応じた適切なアドバイスが受けられます。これを機に、ぜひ医師と相談し、健康的な生活を送る努力を始めてみましょう。
-
生活習慣の改善
- 食事療法: 脂肪分の多い食品を控え、野菜や果物を多く摂ることが推奨されます。特に、飽和脂肪酸の摂取を減らし、オメガ3脂肪酸(魚油など)の摂取を増やすことが心血管疾患のリスクを下げます。
- 運動療法: 定期的な運動は、HDL(善玉)コレステロールを増やし、LDL(悪玉)コレステロールやトリグリセリドを減少させます。週に150分の中等度の運動が推奨されます。
- 禁煙: 喫煙は脂質異常を悪化させるため、禁煙は脂質プロファイルの改善に寄与します。
Q&A
Q1: 脂質異常症の薬は一生飲み続ける必要がありますか?
A1: 脂質異常症の治療は、年齢や併発する合併症、その他リスクに応じて変わります。多くの場合、薬は長期間にわたって必要とされますが、生活習慣の改善によって薬の量を減らすことができる場合もあります。定期的な健康診断と医師の指導に従ってください。
Q2: 脂質異常症の薬に副作用はありますか?
A2: 薬物によっては副作用が生じることがあります。スタチン系は非常に効果が高く、安全性の高い薬剤です。筋肉痛が出たり、血液検査で筋肉の酵素(CK)が上昇することがあります。数%の方に筋肉痛が出ることがありますが、横紋筋融解症になることは極めて希で最近の研究では実際にはないのではないかと言われています。
脂質異常症は適切な治療により管理可能な状態です。生活習慣の見直しと適切な薬物療法を組み合わせることで、心血管疾患のリスクを大幅に減少させることができます。日常生活の中で健康的な選択を心がけることが、病気の予防や治療において非常に重要です。また、医師との定期的な相談を通じて、個々の状態に最適な治療計画を維持し、必要に応じて調整することが必要です。
健康は日々の小さな努力の積み重ねによって守られます。脂質異常症の治療においても、食生活の改善、定期的な運動、禁煙などの生活習慣の見直しは、薬物療法と同様に重要です。これらの生活習慣の改善が総合的な健康増進につながり、より良い生活を実現します。
最後に、治療は個人の状態によって異なりますので、自分自身の健康状態をよく理解し、医師と密接に連携を取りながら、最適な治療方法を選択することが大切です。脂質異常症の管理は一時的なものではなく、生涯にわたる取り組みです。そのため、持続可能な方法で生活習慣を改善し続けることが、病気の予防と健康の維持には不可欠です。
専門医の特性を活かした薬物の治療から生活習慣の改善までライフスタイルに合わせた密着したサポートが可能です。お気軽に、まつもと整形外科 内科までご相談ください🍀
当院の脂質異常症の治療についてはこちらから!!👇
初診のWEB予約はこちらから!!👇
ここをタップしていただくと内科初診:初診の予約画面に移行します✨
TEL予約はこちら
- 📞0942-27-0755
📖参考文献📖
・厚生労働省,脂質異常症 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-004.html
・日本動脈硬化学会,脂質異常症診療のQ&A https://www.j-athero.org/jp/publications/si_qanda/
・日本動脈硬化学会 脂質異常症 ガイドライン https://www.med.or.jp/dl-med/jma/region/dyslipi/ess_dyslipi2014.pdf
